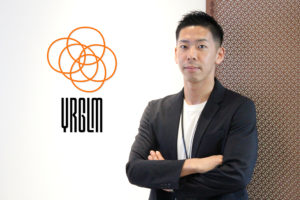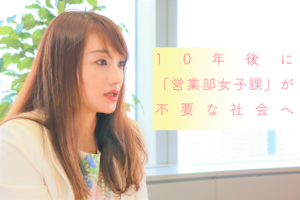マーケティングの自動化・効率化事業を核としてプラットフォームを提供する株式会社イルグルム。その執行役員であり営業本部長をつとめる水野聡志さんは、営業部長になって3年で大きな変化をもたらしました。そこで行ったセールスとマーケティングの2つの領域での取り組みについて話を聞きました。
地道にデータを使ってセールスするプレイングマネージャー時代

ー水野さんのこれまでの経歴を教えていただけますか?
最初は、ウェブ広告代理店の株式会社オプトで制作をやっていました。次に株式会社ぐるなびにEC事業立ち上げのタイミングで転職しました。営業も含めて何でもやりましたね。そして、イルグルム(当時ロックオン) に入社して、2年ほどプレイングマネージャーを経て、現在は営業本部長という立場です。
ーイルグルム(当時ロックオン) での営業では、当初はどのようなことをされましたか?
弊社はもともと開発主体の企業です。それまでは、お問い合わせや反響、広告代理店さんの販売で自然発生的に売上が立っていたんですね。僕が入社したのは営業に力を入れはじめる時だったので、それまでやっていなかったプッシュ型営業を進めようということで、まずアウトバウンド営業を手掛けました。
ーいちからやられたんですか?
当時はひとりでいちからやっていました。僕個人はぐるなび時代にアウトバウンド営業の経験があったんですが、弊社にはその文化がなかったので、僕が電話をしていると周りから「水野さん、知らない人に電話を掛けてるんですか?」と驚かれていました。
ーイルグルム(当時ロックオン) での営業は、どういったところが難しかったですか?
弊社の商品「アドエビス」は、広告の効果測定をするツールです。これで広告を分析することで、結果的に広告運用の質が高まって売上に結びつくというもので、売上アップに直接貢献するイメージを持っていただきにくい商品です。企業様もいろいろ課題がある中で、どうしても検討の優先順位が下がってしまって苦労しましたね。
ー売上に直結しにくいイメージをどう払拭されたんですか?
どの企業様も売上目標は高く設定しているので、現状の延長線上で達成できそうなのかそうでないのかと問題提起すると、難しい場合が多いんですね。「それならば、やり方を変えていかないといけませんよね」ということで、地道にデータを使ってPDCAを回していくしかないということを認識していただきます。また、今やるのが効果的なのかそうじゃないのかという問題提起もして、導入の意思決定を早めていただけるようにセールストークの型を作っていました。
3年で売上3倍という目標

ーマネージャーになって、仕事はどう変わりましたか? また、数年単位のビジョンは見えていましたか?
チーム全体の達成に目を向けられるようになりました。メンバーが売りやすいようなキャンペーンを企画したり、営業経験が浅いメンバーをしっかりと引き上げたりということに専念しています。
2020年までを成長期と捉え、2017年の冒頭に、2020年まではセールスやマーケティングの領域に人員補強も含めて投資して、売上を3倍に伸ばす中期計画を掲げました。そこを目指して、ダイレクトとパートナーの両方を回す仕組みをつくるのが、僕のミッションです。
ービジョンはあっても、どこから手をつけるか戸惑いがあっても不思議ではありません。
営業が高い水準で毎月新規をしっかりと取る。カスタマーサクセス部門がお客様に解約いただかないようなサポートをする。さらに前提として、お客様に喜んでいただけるプロダクトを提供する。われわれはサブスクリプション型なので、その3つが一体となってビジネスを進めます。カスタマーサクセス部門には、解約率をこれくらいに抑えたいという目標があります。おのずと、では営業は新規でこれくらい取らないと支えられないとわかります。そこに向けてどうやっていこうか、という感じですね。
3段階のごくシンプルな戦略とは?

ーでは、実際何から手をつけていったんですか?
営業なので、締め日までしっかりと数字を追いかけていく文化をまずつくりたかったんです。そのために、自分が営業時代にやりにくく感じていたことを潰していきました。それから、営業の数字はチーム全体で達成されてこそ尊いという文化を根付かせる。自分が達成しても他にコンディションがよくないメンバーや状況があれば、チームのために上積んでいくという文化を作りたかったんです。
ー具体的にどのように進めていったんですか?
段階的に3つ行いました。まず、チームの連絡で使っていたグループチャットで、目標売上までカウントダウンするようにしました。受注があるたびに必ずチャットに「いくら取れました」と投稿してもらって、「よし、残りいくらだね!」と数字を意識してもらいます。不思議なもので、目標までの残りの数字を“見える化”すると、そこから数字が伸びる実感がありましたね。
ーそのやり方だと、達成した時の盛り上がりが違いますよね。
2つ目はまさにその盛り上がりの部分なんですが、達成会をすごく派手にやりました。チームが達成した時には会社から経費が出るようにして、最初は居酒屋で飲み会からはじめて。四半期ごとの高い目標達成ができたら、見た目にも映えるようなパーティールームを借り切ったりとか、リムジンを借り切って東京を一周しながら飲み会したりとか、チームで達成するとこんなに楽しいんだという感覚を持ってもらいました。
ーメンバーも喜んでいましたか?
はい。それが“達成グセ”に繋がって、非常に効果がありました。ここまでの①、②は同時にやって、半年後に③として評価制度を見直したんですね。全営業メンバーが個人の目標だけ達成しても査定は100%にならない仕組みです。配分はポジションによって変わりますが、成果の3割はチーム達成目標、残り7割を個人の達成目標という具合です。もちろん、①、②が根付いたから③がスムーズに導入できたと認識しています。
ーその3段階を経て、成果などはどう変わっていきましたか?
年度の前半で①、②をやって、後半で③をやりました。数字は、結果的には面白いように伸びましたね。年度末には月次で倍の売上になるまでに伸び、今は当初の4倍以上の売上ですね。プロダクトに大きい変化はなく、セールスとマーケティングに力を入れたことでここまで伸びました。
部下とのコミュニケーションは「いったん承認してナンボ」

ー当初のメンバーは今でもトップセールスなんですか?
当初のメンバーたちは、今は課長でミドルマネージメントの立場になっていますね。彼ら、彼女らも先ほどの3段階を自発的に実践しているようで、文化が根付いたと感じています。みんなで達成すると楽しいということをしっかり味わってきたメンバーなので、今もその楽しさを率先して踏襲してくれているんじゃないでしょうか。
ーチームが大きくなると下のメンバーとの関わりが難しくなりそうです。どうやって関わっているんですか?
ミドルマネージメントとのコミュニケーションは今でも頻繁に取っていますね。どういう戦略でどう数字を作っていくかを議論します。さらにその下のメンバーとは、2週間~3週間に1回、1対1で面談する時間を取っています。営業本部全体で24~25人いますかね。どちらかというとプライベートな、悩みや支援を求める内容が主ですね。当初は、階層を飛び越えることに迷いがあったんですけど、思い切ってやっています。
ーミドルマネージメントからクレームはありませんか?
僕が聞いた話は課長には伝えています。いちばんやってはいけないのは、課長がメンバーに出している指示や戦略を僕が否定して別のやり方を押すことです。ミドルからは、こういう意図でこういう指示を出しているという話を聞いて、頭に入れておきます。

ーメンバーからするとけっこう近い存在ですね。
そうですね。それでも、多少は怖い存在でしょうから、面談は日比谷公園を散歩しながらやっているんですよ。30分で1周できるコースを、横並びで歩きながら話します。そうすると、意外と本音を出してくれて、距離が近づく感覚があります。具体的な解決策まで提示できないことも多いんですが、「自分が悩んでいることを水野さんが共有してくれた」というところまで持って行ければいいかなと思ってやっています。
ー水野さんの中で、この関わり方はよくなかったというのはありますか?
一時期、“詰める”ことをやっていたんですが、辞める人間も出してしまって、明らかによくなかったですね。感情的になることはないんですが、数字を逆算して「今、何をやらないといけない?」、そのために「これだけ電話します」「毎日このスケジュールで」と具体的な行動を決めて合意させてというふうにやっていました。だから、さしあたっては今の関わり方が僕の中では正攻法です。
ーその関わり方はどうやって身につけられたんですか?
本ですね。コーチングなどいろいろ読みました。やっぱり、人は一旦承認してナンボなんだなと実感しました。
まとめ
組織が変わっていくにつれて自身の役割も変わり周囲から求められることも変わっていきます。水野さんは自身成果を創出する為に組織の在り方や自身のマネジメントの手法まで変え組織の成果を創出することに成功しています。チームに沿ったマネジメントの方法など見いだせてない方は、まず何をすべきかを考察し、それを推進する為に自身が何をすべきかを改めて考えていてはいかがでしょうか。